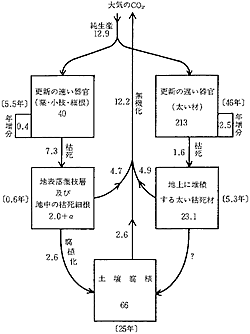| なぜ環境問題に かかわるようになったのか ――生涯をふりかえって 若い世代の方々に伝える―― |
 |
| びわ湖・フブスグル湖交流協会 会長 吉 良 竜 夫 (大阪市立大学名誉教授・滋賀県顧問) |
まえおき |
| これは、2005年1月22日に、滋賀県草津市にある(財)国際湖沼環境委員会の会議室で神鋼環境ソリューション労働組合の若手の方々にお話した講演の原稿をもとに、大幅に改稿・加筆したものです。 |
幼・少年期 |
父親は、住職と小学校教員を兼ねていましたが、さらにもう一つの顔は、今ふうに言えば「典型的なナチュラリスト」でした。貝類の収集ではプロ級で、それまで日本では知られていなかった南方系の淡水産の貝の新種を見つけたりしていました。 後年、現役教員引退後には『原色日本貝類図鑑』(初版1954:保育社)を執筆し、英訳本(1962)も出版されました。おかげで私は、外国の人たちから「そうか、おまえはあのキラの息子か」と言われて、大分おかげをこうむりました。いつも一家で裏山へハイキングにいき(写真2)、珍しい食虫植物やカタツムリの名を教えてくれました。私が自然相手の仕事をし、環境問題と取り組むようにもなったのは、この父親の影響が大きかったのでしょう。
|
||||||||||||
青年期1(高校時代) |
| 1936年に京都の旧制高校に進学して山岳部に入り、それが私の一生の方向を決めることになりました。山岳部の中で何人かの親友ができ、生涯の友としてお互いに影響し合いながら、今日までめいめいの仕事を続けてくることになったのです。 大阪の千里に国立民族学博物館を作り、初代の館長となった梅棹忠夫(うめさお・ただお)君は、その一人です。彼は、動物生態学から民族学に転身し、独特の生態史観に基づいて、世界の文明の構造と日本文明の位置づけを発表して世間を驚かせ、また今日の情報社会の到来や民族間紛争の激化をいち早く予言するなど、たえず文明学の先頭に立っています。1960〜70年代の高度経済成長期にビジネスマンの間でも広く知られたKJ法(一種の発想・総合法)の提唱者、川喜田二郎(かわきた・じろう、KJは彼のイニシアル)君も、おなじ仲間です。構造地質学者で近畿の断層構造に明かるい藤田和夫(ふじた・かずお)君は、神戸は地震の危険が大きいと訴えつづけてきたのですが、なんの対応もされないまま、あの大震災がおこったのでした。彼は、震災直後、兵庫県地域活断層調査委員会の委員長を務めています。ほかに、伴豊(ばん・ゆたか、民族学、フィリピンで戦死)君、和崎洋一(わざき・よういち、地球物理学から民族学へ)君の二人の物故者もいました。 さらに重要なことは、山岳部の先輩にすごい方々があり、当時京大に在籍しておられたことです。日本の生態学・動物社会学の草分けで、日本登山界のリーダーの一人でもあった今西錦司(いまにし・きんじ)さんや、第一次南極越冬隊長だった西堀栄三郎(にしぼり・えいざぶろう)さんなどがその代表格で、しかも高校生たちとの間にさえ交流があったのです。 |
青年期2(大学時代) |
| 私たちの仲間は京大に進学し、それぞれ違った専門分野に進みましたが、そろって今西さんの門下に入りました。いわゆる「今西グループ」に加わったわけです。今西グループとはどんなものだったかというと、それは「学閥」などではなく、めいめいが勝手なことをしながらも、お互いに議論を戦わせて相互に影響を受け合いながら成長していく。梅棹君の表現を借りれば、「団結は鉄よりも固く、人情は紙よりも薄い」、そんなグループでした。当時の今西さんは、山についての総合的な学問「山岳学」、つまり雪や氷の問題から動植物に至る総合的な研究のフィールドワークが一段落し、究極の目標であったヒマラヤへのアプローチが困難な国際情勢のもとで、大陸奥地やニューギニアの探検登山をねらっていました。我々は、未開の大自然のなかの探検にあこがれて、今西さんのもとに入門し、探検家としての訓練を受けることになりました。 初めての訓練は、大学2回生のとき(1941年)、ミクロネシアのポナペ(ポーンペイ)島でした。日本の対英米開戦の直前の夏で、軍はすでに学徒動員を決定していたらしく、私たちが横浜を出帆した直後に「学生の海外渡航禁止令」が出ました。最初にパラオ島に上陸して政庁に挨拶にいくと、いきなり「君らはモグリだろう」と言われました。まさに間一髪でした。このチームには、大学入学後に親しくなった(故)中尾佐助(民族植物学)君も加わっていました(写真6)。彼は、後年、農耕の起源と農耕文化の類型についての独創的なアイディアを発表し、今は広く知られている「照葉樹林文化」という言葉の提唱者となりました。 ポナペ島は、北緯およそ6°の太平洋のまん中にあり、淡路島の60%くらいの面積のほぼ円形で、全島が原生林に覆われたジャングルの島、中央にある最高峰は海抜780m、広大な珊瑚礁とマングローブ林(写真4)にかこまれ、ニューギニア探検を想定した訓練の場としては申し分ありませんでした(図1)。植生調査を担当した私は、初めて熱帯雨林に触れ、とくに中腹以上の高地のみごとな蘚苔林(コケ林)(写真5)には感動しました。しかし、調査が進むにつれて、イメージしたような巨木はなく(写真6)、高木の種類数もごく少なくて、話に聞く熱帯雨林とのあまりの違いに、欲求不満を抱えたままの帰国となりました。それは、太洋島の運命でした。 |
 |
 |
||
| 写真4 | ポナぺ島南岸のマングローブ林で。人物は筆者。 (1941/9、撮影:中尾佐助) |
写真5 | ナペ島、海抜600メートル以上の高地に見られるコケ林。多雨の熱帯高地に発達する森林景観である。(1942、撮影:中尾佐助) |
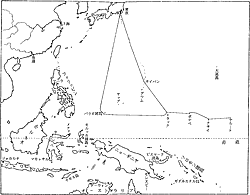 |
 |
||
| 図1 | ポナペ島の位置と調査隊の航路(今西、1944により、修正)。地名の表記は当時の慣習のままとした。 | 写真6 | ポナペ島山地のコシダ草原で。左から吉良、中尾、今西、川喜田、梅棹(1941/9、撮影:森下正明)。 |
| 大洋島の生態系は、遠く海を越えて、たまたま到達できた少数の種類の生物だけから構成されています。構成生物の種数が少ないのは当然で、偶然手にはいった部品だけで組み立てた機械のようなものですから、非常に安定性に乏しく、新しい外来生物が入ってくると、たちまち構造が変わります。森林の構成種で最も多いのはヤシの1種で、栄養分に富んだ実をたくさんつけますが、それを食べる野獣(哺乳動物)は全くいなかった。そこへ、大航海時代の船員が、次に寄港したときの食料にとブタを放したところ、たちまち野生化して増え、最も重要な狩猟獣になっていたのは、その適例です。 実は、この現象は、湖の生態系にも共通しています。湖と島とは、写真でいえばネガとポジの関係で、湖は、陸の海に浮かぶ水の島だからです。琵琶湖でも、動物ではいま論議の的になっているオオグチバス、植物ではコカナダモ(写真7)のような外来生物が猛烈に増殖して、在来の生態系の構造を変えつつあるのは、同様の現象です。ポナペで経験したこうした視点が、ずっと後年の琵琶湖での仕事に役立ったのは、珍しい偶然でした。 ポナペ島遠征について長くお話ししたのは、それが私にとって非常に大きな意味をもっていたからです。今西隊長と、今西グループの先輩である昆虫生態学者(故)森下正明(もりした・まさあき、九大・京大名誉教授)副隊長との言動から、総合的な自然と住民生活の理解、未開の森林を踏破する技術を学び、一方で、のちに熱帯林についての欲求不満を解消するために東南アジアで活動する原動力をえたのでした。 第2回目の探検は、翌1942年、戦時下の中国(当時の「満洲国」)で行われました。対象は、かねて今西さんがねらっていた中国の東北端、大興安嶺山脈の北部で、北海道がスッポリ入るほどの面積が一面のカラマツ(ダフリアカラマツ)の樹海(写真8)に覆われている地域です。もっともらしく詳細に等高線や水系の入った地図はあったが、全くの捏造品で、ひどいしろものでした。満州国成立後、航空写真撮影はほぼ終わっていたが、なお未撮影の白色地帯が残っており、三角点測量による正確な地図化にはまだ遠い状況でした。数人の日本軍人とヨーロッパ人学者とが中央部まで入った記録しかなく(図2)、満洲国の研究機関による学術調査はことごとく失敗に終わっていました。 調査の許可と経費を捻出するために、伴君が先発して新京(いまの長春)に長期滞在して、満洲国の軍部とねばりづよく折衝し、その熱意で軍人たちを説得して、ついに一般人立ち入り禁止地域の旅行許可と、「匪賊討伐」「兵要地誌調査」などの名目でかなりの経費の負担を承知させました。軍の企画ですから、出発のときは学生たちもお仕着せの軍服姿でした(写真9)。 |
 |
 |
||||||||
| 写真7 | コカナダモ。北米原産の水草で、1961年に初めて琵琶湖で見つかり、数年で全湖に広がって大繁茂している(1988/7)。以下、撮影者名のついてないものは、筆者撮影。 | 写真8 | 大興安嶺のダフリアカラマツ林。わずかにコウアンシラカンバが混じっている(1942/6、撮影:藤田和夫)。 | ||||||
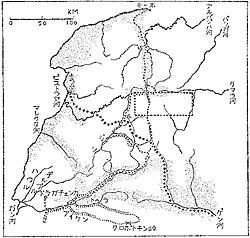 |
 |
||||||||
| 図2 | おもな探検隊の行程(今西、1952から取る)。
|
写真9 | 大興安嶺探検隊本隊、軍服すがたでハイラル出発。前列左端が吉良、その右が今西隊長(1942/5/12、撮影:小川 武)。 | ||||||
| これまでの調査隊の失敗の原因は、食料・装備の輸送に使った馬車では、谷をうずめた湿地が通れなかったからでした(写真10)。大量の馬の飼料を運ぶためには馬車の数が増え、それがまた通過の障害になるという悪循環になったようです。我々は、人工飼料を必要とせず草だけで働けるモンゴル馬と白系ロシア人の馬夫に輸送をゆだね、主食と乾燥食品以外の食料(魚と鹿・鳥)は現地調達という大胆な戦略で問題を解決しました。大興安嶺西麓の白系ロシア人の集落を出発してから中国北端のアムール川沿いの町モーホ(漠河)まで、満2ヵ月の行程(図2)は、終始谷沿いの湿地と戦いながらの行進でした(写真11)が、1頭の馬を失っただけ、危惧された隊員(総勢21名、うち学生10)、案内人・人夫たちはすべて無事でした。 |
 |
 |
||
| 写真10 | 北国特有の谷地坊主(やちぼうず、スゲ類がつくる株立ち)の密生した湿地のなかを難行する馬車。スゲはまだ芽を出しておらず、ほとんどが黒く野火で焼けている(1942/5/18、大興安嶺、ガン河中流、撮影:小川 武)。 | 写真11 | 明けても暮れてもグラグラする谷地坊主の頭の上をたどり、踏み外しては水に落ちながら行進した(1942/5/28、大興安嶺ガン河上流、撮影:小川 武)。 |
| 地図のない地域での進路の確認には、ポナペ島への航海で知った六分儀を陸上で使う方法を開発して経緯度を測定しました(写真12)。白色地帯を含む河川水系の解明、北部大興安嶺の最高峰の登頂(写真13)、全域の地質・地形調査、満洲からの未記録植物20数種を含む広範な動植物の採集と生態観察、狩猟民族ツングース(写真14、15−1、15−2)の調査など、科学的成果は大きかったのですが、ここでは立ち入りません。ただ、なぜここに、西シベリアや沿海州・サハリンなどのエゾマツ・トドマツの常緑タイガとは異なった、カラマツの落葉タイガがあるのかを明らかにしたことは、現在関わっているモンゴル国北部の調査との関係で、簡単に述べておきましょう。 |
 |
 |
||||
| 写真12 | 六分儀による天測。水銀をたたえて作った人工水平面に向かって六分儀を構えている藤田和夫と、クロノメーターで測定時刻を読んでいる筆者(大興安嶺ガン河上流、1942/5、撮影:小川 武)。 | 写真13 | 北部大興安嶺の最高峰オーコリドイ山(標高約1,550m)の頂上で。背後の最高点に国旗を立て、ハイマツの茂みの間で休憩する。左から今西、筆者、二人おいて伴(1942/6/23、撮影:小川 武)。 | ||
 |
|||||
|
|||||
 |
 |
||||
| 写真15−1 | 興安嶺北端部のカラマツ林地帯で移動・狩猟生活をいとなむ「トナカイ・オロチョン」。 | 写真15−2 | 100年前以後にロシア領から移住してきた人たちで、洋服・ギリシャ正教・パン食などの洋風文化になじんでいる。トナカイはミルク供給と運搬用だが、小型で女性しかのれない(1942/7、撮影:森下正明・小川 武)。 | ||
植生調査担当の川喜田君と私は、東シベリアの気候を調べて、こう考えました。 「このカラマツ林地域は、中央アジアからモンゴルを経て北東方向にのびている乾燥地帯の端にあたり、雨量が少ないため、最終氷河期には大陸氷河(氷床)に覆われることなく、植生のない寒冷砂漠だった。その結果、寒気が地下深く浸透して、数十ないし数百mもの深さの凍結層を形成した。氷期が終わって温暖化しても、夏に地面の表層1〜数mしか解けず、それ以深は凍ったままで「永久凍土」となっている。夏に集中して降る雨の量は少ないので、もし永久凍土がなければ、「森林ステップ」と呼ばれる程度の疎林の小団地しかできないはずだが、水を透さない永久凍土層のおかげで表土に水が保存され、凍結と水不足に強いカラマツの密林ができているのだ(図3)。」 この考えは、ごく最近の日本の生態学者によるシベリアでの研究で、立証されつつあります。 このような成果をあげたほか、私たちは、戦後の日本では最初の探検らしい探検の経験から、未開地での自然研究に自信をもてるようになって帰ってきました(写真17)。私個人にとっても、学生時代のわずか2年間に、地球の温暖湿潤の極から寒冷乾燥の極までを経験したことは、何ものにも代えがたい財産となりました。晩年になって、また、永久凍土上にカラマツ林の茂る北モンゴルに通っている(後出)のは、この経験を反芻しているようなものです。 |
||||
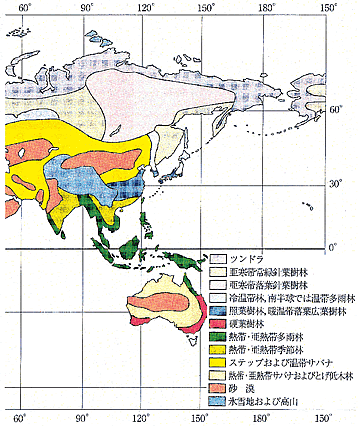 図3 簡略化した東アジア、西太平洋の植生図(吉良、2001から取る)。 |
||

|
| *[参考] 今西錦司(編著)(1944) 『ポナペ島――生態学的研究』彰考書院。復刻版(1975)講談社。 今西錦司(編)(1952) 『大興安嶺探検――1942年探検隊報告』毎日新聞社。復刻版(1975)講談社。 文庫版(1991)朝日文庫 い26−1。 |
壮年期 |
| 大興安嶺から帰った直後に私は結核を発病し、太平洋戦争への従軍はまぬがれましたが、十数年間はフィールドワークができませんでした。その間に、偶然にも梅棹・川喜田・藤田・吉良の4人はそろって新設の大阪市立大学に職を得ました。そこでも私は、ずっとデスク・ワークと実験的研究を続けていましたが、ポナペ島で感じた欲求不満は根強く、本格的な熱帯雨林の研究への思いは強くなる一方で、自分の健康は棚に上げて、なんとか東南アジアに調査隊を出したいと画策し始めました。そして、タイのバンコクで太平洋学術会議が開かれた機会に、梅棹君を隊長に大阪市立大学第一次東南アジア調査隊(1957〜58)を送り出すことができました。この隊には、私の若い同僚2人、小川房人(今は大阪市大名誉教授、元・大阪市立自然科学博物館長)君・依田恭二(故人、大阪市大教授・滋賀県立大教授を歴任)君が参加し、初めて熱帯林の研究に挑戦しました。しかし、隊長たちがカンボジア・ベトナム・ラオスと回っている間に調査できたのは、東北タイの乾燥地帯の疎林植生だけで、ねらっている雨林研究とはほど遠いものでした。 やがて私も健康を回復し、第2次隊(1961〜62)ではタイ領マレー半島で、第4次隊(1964〜65)ではカンボジア南西部で、湿潤熱帯林の調査に加わることができました。けれども、これらの地点の気候には年に1〜2ヵ月の明瞭な乾季があり、森林も典型的な熱帯雨林ではなく、「熱帯季節林」と呼ばれるものでした(図4)。最も見やすい森林発達の目安は、森林の最上層をなす大木の高さで、東南アジア赤道地帯の熱帯雨林ではそれが60mを越えます(後述)が、これらの森林では40m台にとどまっており、私の心の中の不満は、またしても満たされなかったのです。 |
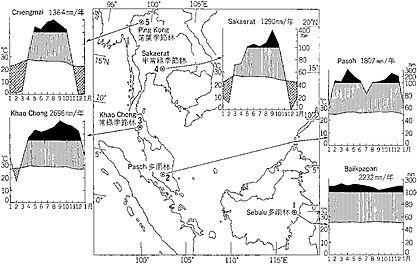
|
3年間の折衝を経て、日本・マレーシア・英国の3国は、マレー半島内陸部の北緯3°にあるパソー保護林(図4)で、協力して原生熱帯雨林の生態系研究を行うことになりました。日本隊には、4年間(1970〜74)に全国の研究機関から34名が、延べ205人・月にわたって参加し、生態系研究のほとんどの主要部分を担当しました。現地から38kmの町に1軒の家を借りて本部兼宿舎とし(写真18)、1棟の実験室を増築してかなり高度な機器をそなえ、さらに調査地の入り口には作業小屋(写真19)を建てました。野外研究は、パソー保護林1,300haのうち、ゆるやかに起伏する平地部で行いました。 とくに詳しく調べた2haの調査区には、幹の胸高直径(DBH)20cm以上の高木が277種もあり、しかもそのうち114種は1個体しかありませんでした。次の1本を見つけるには、広い林の中を探しまわらねばならないというわけです。地上から30〜35mの高さに連続した林冠層があり、その上に点々と最上層の木が抜き出ています。その樹高は50m台。樹高はやや低いが、まずまず典型的な熱帯雨林でした(写真20、21)。研究の成果は、きわめて多岐にわたり、項目をあげるだけでも長い紙面が必要ですが、ここでは1つの話題にとどめます。 |
||||
 |

|
||||
| 写真18 | IBPマレーシア研究日本隊の本部。調査地パソー保護林にもっとも近い町クアラ・ピラの借家。1970〜74の3年半の間借りて使った。 | ||||
 |
|||||
| 写真19 | パソー保護林入り口に建てた現地小屋を出発する伐採作業チームと人夫たち(1973/3)。 | ||||
| その第一は、この森林の生きた植物体の現存量(バイオマス)の動態――光合成で大気中から二酸化炭素を取りこんで有機物を生産し、その一部は植物の呼吸のために消費されるが、残りがバイオマスになっていく。一方で植物体は枯れてバイオマスは減少し、地上や地中で分解されてまた二酸化炭素になって大気中にもどる――の全過程を、炭素の動きとして定量的に測定できたことです。図5のようにまとめると、3年ほどの期間の平均でこの森林は、乾燥重量にして1haあたり約99トンの有機物を、光合成によって生産していました(総生産量という)。しかし、その4分の3ほど(74%)は植物の生活に必要な呼吸作用の原料としてすぐ消費されて、あとに残りません。新しい植物体となって残るのは4分の1(26%)だけです(純生産量)。ただし、それだけバイオマス(土地面積あたりの生きた植物体の存在量)が増えるわけではなくて、一方で立ち木が枯れたり、古い葉や枝が枯れ落ちたりしてバイオマスが減るので、純生産量の4分の3ほどはその埋め合わせに使われ、結局、森林全体のバイオマスは1年・1ヘクタールあたりに、わずか5.3トン(総生産量の5.9%)しか増えないことになってしまいます。 |
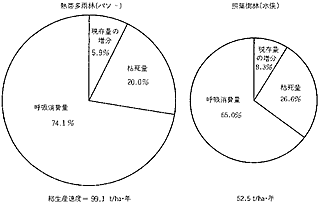
|
だから、よく発達して定常状態に達している森林は、大気中の二酸化炭素にとっては供給源(ソース)でもなければ、吸収源(シンク)でもないのです。そうでなければ、どんな生態系も、限られた地球の環境のなかで存続しつづけることはできない。これは、当然のことです。しかし、もし森林を焼き払って開発(写真22)したら、バイオマスがもっている炭素は、二酸化炭素になって一挙に大気中に放出されます。この森林は、地上部だけで乾燥重量475トン/haですから、その半分の炭素量は莫大なものです。地下の根も、やがて枯れて分解し、徐々に二酸化炭素を放出していくでしょう。 20世紀末ころには、熱帯林は1年あたり1,000万haずつ開発されていたといいます。熱帯林の地上部平均バイオマスを300トン/haと見積もると、完全に焼き払われたとき放出される二酸化炭素中の炭素量は、およそ15億トン、化石燃料(石油や石炭)の消費から発生する量の4分の1くらいに相当する。これは大変なことです。正確な実測に基づいてこういう見積もりができたのは、当時としては世界最初だったと思います |
||||

|
| *[参考] 吉良竜夫(1983)『熱帯林の生態』人文書院。 |
環境研究への転身 |
| 私が初めて大気中の二酸化炭素濃度の急激な上昇と地球温暖化の可能性について知ったのは、高校山岳部の後輩、樋口敬二(当時、名古屋大学教授)さんに教えてもらった、一般向け科学誌サイエンティフィック・アメリカン(1959)へのプラース(G. N. Plass)の寄稿を読んでからでした。学生のころドイツの生態学者ルンデゴールド(H. G. Lundegardh)の第二次大戦中の研究「自然界での酸化炭素の循環」(1945)を読んで以来持ち続けてきた炭素循環への興味、上述のようなマレーシアの熱帯雨林での経験などが重なって、地球環境への関心がにわかに深まりました。身近な公害問題からではなく、地球規模の現象への関心から環境問題に取り組み始めたのは、やや変則的な経歴だったといえるかも知れません。 環境問題についての最初の考察「自然のなかの人間」(朝日ジャーナル)を書いたのは1968年のことでした。これがメディアの人たちの目にとまり、中央公論社から生態学から見た環境問題についての執筆の注文がきました。時期尚早と辞退したのですが、鹿児島で開催中の学会の場まで追っかけてこられた編集者の熱心にほだされて、一晩の徹夜で書き上げたのが「環境問題への生態学的アプローチ」でした。中央公論(1970)の巻頭論文として出版されたときには、原題は副題となり、「危機の学としての生態学」という主題がつき、びっくりしました。この題目が当たったのかどうか知りませんが、すぐに1〜2の単行本に転載されて、広く知られるようになりました。このような経過で、本人の思惑とは関係なく、私は「環境屋」のレッテルを貼られてしまったようです。 1960年代の終わりが近づくと、環境問題はにわかに世界の関心の的となり始め、近未来の食糧不足を想定して始まったIBPも、終了のころには、その成果が環境問題の基礎資料としてより高く評価されるようになりました。IBPの陸上生産部門の国際委員だった私は、1969年からは国際学術連合(ICSU)の環境問題科学委員会(SCOPE, 1969〜)の初代委員にも選ばれ、第1回の国連環境会議(1972、ストックホルム)の開催への準備にも関わりました(会議そのものには出なかった)。 日本国内では、戦後まもないころから水俣病や四日市ぜんそくといった激しい公害問題が発生した関係で、早くから「公害」についての関心は高かった。しかし70年代になると、内湾・湖沼・河川・土壌などの汚染・汚濁、酸性雨、光化学スモッグなど、より広い地域の現象が目立つようになり、局地的な公害を含みながらより広い視野から見た「環境問題」への対応・研究の緊急性が、一般社会にも理解されるようになりました。文部省(当時)も、1975年からは、科学研究費のなかに「環境特別研究」の枠をもうけて、研究の促進をはかりました。 私は、思いがけないいきさつから、この枠内で「琵琶湖とその集水域の環境動態」という特別研究(1977〜79)の代表者を引き受けることになりました。実は、そのときすでに、私と滋賀県・琵琶湖との間には、かなり深いつながりができていました。1971年に滋賀県の委嘱で「21世紀のびわ湖――びわ湖の未来に関する調査研究」というテーマのプロジェクト・チームができ、メンバーには、梅棹忠夫、上田篤、樋口敬二などの友人や私を含む「広義の滋賀県人」――本人または家系が滋賀の出である人たち――が集められました。ちなみに、私の父は大津生まれで、幼いころに大阪に養子に出されていたのです。その報告書(1972)のなかで、私は、「鎮守の森」を材料に将来の滋賀の自然保護のあるべき方向を論じていますが、その因縁で、1972年の後半には、やはり県からの依頼で、大阪市大のメンバーを中心に『滋賀県の自然保護に関する調査報告』(l972)をまとめました。1975年からは、新しく発足した滋賀県自然環境保全審議会の委員、さらに会長を務めることになっていました。 この科学研究費のまとめが終わろうとしていた1980年、当時の滋賀県知事、武村正義さんから、滋賀県に琵琶湖研究所を作って所長になってほしいという要請がきました。そのころ琵琶湖は、富栄養化をおもな原因とする水質の急激な悪化で、京阪神の「水がめ」としての役割に深刻な危機が生じていたのです。そのとき私は、大学の定年63歳にあと2年を残すだけの年齢でした。近江の国は父の故郷でもあり、また高校の山岳部時代に歩きまわっていた比良・鈴鹿・湖北の山々の自然にまた調査を通じて親しみ始めていた時でしたし、大学内で少し居づらい事情もありましたので、その誘いを受けるのに躊躇はありませんでした。また武村知事が、就任以来、県民と協力して製造元の会社の抵抗と戦い、琵琶湖の汚染の元凶物質の筆頭であるリンを含んだ洗剤の追放に成功された姿勢も、大きな魅力でした。 1981年9月末に大阪市大を辞職して、すぐ滋賀県琵琶湖研究所設置準備室長、82年4月には組織が発足、年末に建物が完成して(写真23)、研究職所員は15名のささやかな研究所が発足しました(写真24)。それまでずっと陸生植物の生態学をやってきた私が、湖や川の研究(陸水学)については常識以上の知識も経験もなかったのに、なぜ無謀にもこの職を引き受けたのか。 |
 |
 |
||
| 写真23 | 20周年を迎えた琵琶湖研究所(1994/12)。 | 写真24 | 琵琶湖研究所開所式(研究所大ホール、1982/12/1)。武村正義知事のあいさつ(撮影:琵琶湖研究所)。 |
その理由は、湖のもつ基本的な性格からきています。先に、島と湖との生態系が共通の性質を持っていると申しましたが、島を取り巻いているのが均質な海であるのに対して、湖のほうは、降った雨水がその湖に流れこむ一定範囲の陸地(集水域)に囲まれている点が、両者の大きな相違点です。集水域の環境は、地形・地質・気候・生物界といった自然条件と、人間活動の種類・強度に応じて湖ごとに千変万化しており、湖の環境を左右する最大の条件となっています。湖そのものの環境と集水域の環境とは、いわば切り離しがたい一つのシステムをなしていて、集水域についての十分な理解がなければ、湖そのものだけをいくら研究しても、その環境を理解し適切に管理していくことはできません。だから、湖の環境の研究所は、陸水学と陸上環境学と両方の研究者から構成すべきである。そういう研究所を作りたいというのが、私のねらいでした。世界の著名な湖沼研究所で、正規のスタッフに陸上環境研究者をもち、所の目的として湖・集水域の統合的研究をかかげているところは、少なくとも当時はなかったと思います。
今年(2005)の6月、県庁内の組織変えで、琵琶湖研究所は23年の歴史を閉じて、県庁内の環境測定部局と合体して、新しい「滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター」に移行しました(写真25)。願わくは、琵琶湖研究所の伝統の優れた部分を継承して、新しい成果を生んでいってほしいものです。 |
||||
| *[参考] 吉良竜夫(1971) 『生態学からみた自然』河出書房新社。文庫版(1983)河出文庫727A。 滋賀県琵琶湖研究所(編)(2005) 『滋賀県琵琶湖研究所記念誌 ――環境科学研究センターへの移行にあたって』(所報22号)。 |
湖沼環境保全の国際活動 |
| 琵琶湖研究所への転身を決めたとき、私は、若いころから慣れ親しんできた近江の国の美しい自然を対象に研究生活を楽しみ、父の故郷の人々、ひいては京阪神のためにいくらかでもお役に立つ余生を静かに送ることを期待していました。しかし、現実はまったく違った方向に動きました。 研究所の建物がまだ未完成で仮事務所にいた1982年の初夏のころ、武村知事から使いがきました。呼び出されたのは部長会議の席で、知事から「2年後に大津で〈世界湖沼環境会議〉をやろうと思う。協力してもらえますか」という問いかけがありました。あまりに突然で、まるでイメージがわかない。とにかく県が決めたことだから「できるだけの協力はさせていただきます」という月並みの返事しかできませんでした。すぐ新聞発表があり、知事は「会議の内容は琵琶湖研究所長にまかせた」と言っておられるらしい。なるほど、政治家はこんなふうに人を使うのか。赴任の際には想像もしなかった、国際活動に忙殺される生活の始まりでした。 企画準備委員会ができ、座長を仰せつかりましたが、委員の方々はきわめて積極的で、すぐに会議の輪郭が浮かんできました。しかし、そのころは、地方自治体が国際会議を主催するなどは論外で、東京あたりでは「滋賀県は一体なにを考えているの」などとひやかされたりしました。今では珍しくもないが、あえてその冒険に先鞭をつけた武村さんのパイオニア精神と見識は、見あげたものです。会議の成立の可能性を探るため、同年の夏には、チェコ・スイス・イタリー・フランス・スウェーデンで湖沼研究所と指導的研究者を歴訪し、意見を求めました。どこでも、旧知のように親しく迎えてくれ、会議の企画にも好意的でした。会議資料として用意する『世界湖沼環境データブック』の初版本に収録する世界のおもな湖・集水域の環境状況、環境保全対策などのデータを集めるため、会議に先立って中国とタイに派遣されたのですが、当時はデータの国外流出に神経質だった中国でも、研究者たちが苦心して、正規のルートを経ずに内々でデータを供給してくださった好意は、感動的で忘れることができません。
もともと武村知事のこの会議への期待は、世界各地の湖での経験を聞いて琵琶湖の環境保全の参考にしたいということでした。ところが意外なことに、多くの参加者が、琵琶湖での保全活動・施策とその成果とを高く評価してくれたのです。会議の意義も認められ、ハンガリーの参加者が「第2回の会議をぜひわが国で」と申し出られたほどでした。これは、世界の湖の現状が、環境保全と持続可能な利用をめざす管理という点で、想像以上に不満足な状態にあることを実感させ、その後の滋賀県の行動に大きく影響しました。 UNEP(国連環境計画)の当時の事務局長トルバ(M. K. Tolba)さんも、この会議の意義を高く評価し、基調講演のなかで「会議はきわめて有意義だけれども、終わればやがてインパクトは薄れてしまう。会議の成果を将来に生かすために、その精神を継承して成果の実現をはかるための国際機関――滋賀委員会ともいうべきもの――を作るべきだ」と提案されました。 武村さんは、すぐこの提案に反応し、翌1985年夏にナイロビのUNEP本部での管理理事会に出席して、国際湖沼環境委員会(International Lake Environment Committee, ILEC)の設立への支持をとりつけました。そして、同年末に発起人会、翌86年2月には琵琶湖研究所での設立総会(写真27)と、わずか半年で発足にこぎつけたのです。2年後には同名の財団法人ができ、当初の委員会はその「科学委員会」となりましたが、財団の活動の中心であることに変わりはありませんでした。
今日まで20年の間に、委員は次々と交替しましたが、いつも十数ヵ国、20人弱の各界の権威者で構成されています。成立のいきさつ上、1995年までの10年間は私が委員長を務めました。湖沼研究の最高権威ともいうべき委員が何人もいる席で、湖沼学には素人同然の私が座長を務めるのは大変な重荷でした。すべての委員から十分に意見を求めてからでないと何事も決めない、というのが私の取った道でした。のちに第2代の委員長になったデンマークのヨルゲンセン(S. E. Jφrgensen)さんなどは、まだるっこしいらしく、「もう少し会議の進行を早めたら」という意味のことを言われたこともありました。「私は大学で学部長の職が長かったのですが、日本の大学の教授会はそれではダメなんです。急ぐと決まるものも決まりません」というのが、私の真意でした。 ILECの当面の仕事は、第2回以後の世界湖沼会議の開催地の交渉と準備、英文の『湖沼管理の手引き』(写真28)、『世界湖沼環境データブック』(写真29)の出版などで、国際事業の皮切りは、中国雲南省昆明市での湖沼管理に関する国際研修コース、6ヵ国(アルゼンチン、ブラジル、デンマーク、ガーナ、日本、タイ)での小・中学校レベルの環境教育プロジェクトなどでした。世界湖沼会議のほうは、開催希望の申し出が多く、第2回(1986)は滋賀県と姉妹関係の米国ミシガン州(ヒューロン湖)で、以後ハンガリー(1988、バラトン湖)、中国浙江省(1990、西湖)、イタリー(1993、マジョーレ湖)、茨城県(1995、霞ヶ浦)と続き、さらにアルゼンチン・デンマーク・再度の滋賀開催を経て、2005年秋には初めてアフリカ(ケニア)での開催が予定されています。 |
||||||||
 |
 |
||
| 写真28 | 『湖沼管理ガイドブック』。1989〜99の間にテーマ別の10冊を発行した。 | 写真29 | 『世界湖沼環境データブック』。世界の217湖沼の自然・社会環境、環境保全対策などのデータを、入手順に4冊のファイルとして出版し(1988〜94)、のちに「アジア・オセアニア」「ヨーロッパ・アフリカ」「南北アメリカ」の3分冊の縮刷版(1993〜95)にまとめた。 |
| 私は、家族の事情で第7回以後は出席できなくなりましたが、それまでの期間は、開催前年の打ち合わせのほか、各種の会議などの機会が多く、滋賀県と姉妹関係を結んでいるミシガン州、ブラジルの南リオ・グランデ州、中国の湖南省をはじめ、そのほか中国では雲南省・遼寧省、アマゾン、タイ、フィリピン、インドネシア、ケニア、ヨーロッパ各地、などの湖沼を訪れて、大いに知識をふやしましたが、これらの経験を通じて、第1回の世界湖沼会議で受けた印象は、さらに確実なものとなりました。 1992年の地球環境サミット(リオデジャネイロ)のころから、地球規模での水(淡水)の不足が、近い将来に危機的な問題になるだろうという認識が、急に高まってきました。『世界人口の増加とともに水の消費も急激に増加するのに、利用可能な水資源の量のほうは、不適切な利用の結果、逆に減少しつつある。したがって2025年には、世界人口の3分の2が水不足に陥るだろう。』という予測が国連から発表されるという事態になっているのです。 ある瞬間に地球表面上に存在する液体状の淡水の99%は、湖に貯えられています。1%の川水は、たえず流れているので、利用可能な量はずっと多くなりますが、1年間の総河川流量を計算しても、湖の貯水量の4分の1くらいにしかなりません。湖の貯水量を減らさないように保ちながら年間に利用できる湖水の量は、河川の総流量の3倍と計算されます(注)。淡水資源としての湖の潜在能力の大きさは、明らかです。 現時点では、ドイツ・スイス国境にあるボーデン湖(コンスタンス湖)や琵琶湖のように、莫大な数の人口の水源となっている湖は、まだそれほど多くはありません(琵琶湖と流れ出す淀川との水に依存している人口は1,400万人、ボーデン湖では、湖からの直接取水を使っている人口が400万人)。しかし、同様な天然湖・ダム湖の数はどんどん増えていくでしょう。ところが、世界的に見て、湖の環境管理は非常におくれており、工業・農業・生活廃水の流入による水質悪化、流域の荒廃・過度の取水・気候温暖化による湖の水位低下ないし干上がりなどの例には事欠きません。この事態を改善することこそ、ILECの最も重要な任務であることは明らかです。 水問題の緊迫状態に対応して、1996年以後、世界水会議(WWC)、地球水パートナーシップ(GWP)などの国際組織ができ、WWCは2000年に「世界水ビジョン」を発表して、水資源の適切な管理の緊急性をひろく訴えました。しかし、その内容は一般的すぎて、湖に関するかぎりは、具体性に欠けほとんど役に立ちません。琵琶湖研究所長の中村正久さんは、ILEC科学委員会の中核メンバーとして、2002年8月、南アフリカのヨハネスブルグで開かれた環境サミットで、新しく「世界湖沼ビジョン」を作る必要性を訴えました。その場で多くの支持を得て、すぐに国際委員会が組織され、数回の会合を経て、2003年3月、WWCが主宰して京都・大阪・滋賀で開かれた第3回世界水フォーラムでの発表にこぎつけました。 このレポート(World Lake Vision―A Call to Action)は、すでに数ヵ国語に翻訳されていますが、日本語訳も2005年1月に出ました。私は、湖沼ビジョン国際委員会の委員長でしたが、実際は名目だけで、実務は南西テキサス州立大学のラスト(Walter Rast)さんが大半を担当してくれましたので、せめて邦訳本の出版だけには力を入れました。それが、ILECでの最後の仕事になりました。 |
| *[参考] Cosgrove, W. J. & F. R. Rijsberman(2000):
『世界湖沼ビジョン;湖と人、共存の道をひらく』新樹社、東京。 吉良竜夫(1990):『地球環境のなかの琵琶湖』人文書院、京都。 *[注] この計算値は、合田 健(1983)から引用した。 |
最後のフィールド・ワーク |
| モンゴル国の北部にフブスグル湖という美しい湖があることを認識したのは、琵琶湖研究所とILECとの協力で『世界湖沼環境データブック』(1988〜94)の編集に着手したときでした。やがて、モンゴルの専門家から正確な情報が提供されてデータブックに収録され、この湖が、バイカル湖への最大の流入河川セレンゲ川の水源をなすモンゴル最大の淡水湖(水面面積は琵琶湖の4倍、最大深度262m)であって、人間活動の影響のきわめて少ない原始的自然環境を保っており、世界の湖沼環境にとって比較基準となりうるような存在であることが明らかになってきました(図7)。 ただちにその重要性を認識した琵琶湖研究所や京都大学の陸水学者たちは、さっそく1996年からこの湖の継年観測を始めました。この湖の沿岸には、南端に近くにハトガル、北端に近い東岸にハンフという2つの小集落があるのですが、観測を始めた縁で、ハトガル出身の青年が琵琶湖研究所に留学することになり、にわかにフブスグル湖は私たちに身近な存在になりました。 |
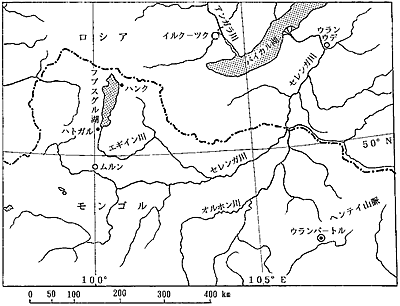
|
| 1998年には、私も初めて観測行に参加しました。黒潮の色を思わせる紺碧の水色、湖のどの部分でも20mもある湖水の透明度、夏も残雪をいただく沿岸山地の眺めなどの魅力は、たちまち私をとりこにしました(写真30)。そして、さらに私にとって決定的なインパクトだったのは、この湖の集水域が、東シベリア内陸部を特徴づけている「明かるいタイガ」の延長上にあり、先に大興安嶺について述べたように、地下に広く永久凍土が存在し、特有の落葉針葉樹(カラマツ)林に覆われていることでした。緯度も大興安嶺とほぼおなじ北緯51度、私の生態学の出発点となり基礎ともなった探検の場、大興安嶺のカラマツ林と同じ自然が、半世紀以上の後また私の前に現われたのです。故郷に帰ったような気持ちで、即座にここを老後の最後のフィールドワークの対象にしようと決めました。先に述べたように。湖の環境と集水域の環境とは一体のシステムをなし、前者の理解には後者の研究が不可欠ですから、このすばらしい湖の環境を守るためには、これはぜひ必要なことでもありました。幸い、私的にもいくらか行動の自由ができたので、それから昨2004年まで、毎年1〜2回現地に通いつめることになりました。 湖そのものの研究成果の紹介は省きますが、琵琶湖と同様に、地殻運動によって東西方向に圧縮されてできた構造湖で、南北に細長く、中ほどに島があること、西岸に接して湖面からの比高1,500mくらいの高い山脈が連なり(写真31)、それに対して東岸側は山が低いこと、最も水深の深い地点は西岸近くにあることなど、地形の特徴に琵琶湖と共通点が多いのが興味を引きました。琵琶湖との大きな相違点は、より大きく深く、高緯度にあり、水面が海抜1,645mという高地にあることでした。 |
 |
 |
||
| 写真30 | フブスグル湖南部。東南岸から北西方向を見た風景。対岸(西岸)には、高い山脈が連なっている。最高峰は海抜3,000mに近い。(2000/8/16)。 | 写真31 | フブスグル湖東北部。中央遠くにハンフの村が見える。背後の高い山々は、ロシアとの国境山脈で、右手のカール(圏谷氷河の跡の円形の凹み)に残雪のある高峰は、海抜3,441m(2004/7/16)。 |
| モンゴル国内で、森林植生が大面積の連続した団地をなしているのは、フブスグル(HB)湖を含む最北部山地と、ウランバートル(UB)の北東にあるヘンテイ山脈との2ヵ所で、前者だけが、「明るいタイガ」のカラマツ林です。これは、すでに大興安嶺で経験ずみの自然だから、私にとって理解するのは簡単だろうと思っていたのですが、ぶつかってみると、どうしてどうして、初めて出会う現象、わからないことが続出し、我々は、それを「フブスグルの七不思議」などと称していたくらいです。自然環境だけでもそうですから、まして人々がそれをどのように利用しているかによって形成されている現実の環境・環境問題を理解することは容易ではない、早合点は大きな誤りをおかすということは、いくら強調してもしすぎではありません。 七不思議の一例をあげてみましょう。大興安嶺では、森林のなくなる高さ――森林限界高度――は約1,400mで、1,500mをこえるいくつかの高峰の森林限界以上の高山帯は、日本の高山とおなじハイマツの低い茂みでした。 ところが、1,600m以上もあるHB湖のまわりの山々は、樹高20mをこえるカラマツの林に覆われているのです。しかも、西岸山脈での森林限界は、およそ2,200mという、他地域とくらべて異常に高いところにあるのです。植物の分布は夏の生育期間の温度に支配されるので、冬がきびしくても夏が比較的暖かくなる大陸性気候下では、植生帯の分布限界高度が高くなることは生態地理学の常識ですが、湖畔のハトガルにある測候所の気温観測値からも、こんなに高い値は説明が困難で、まだ疑問として残っています。大興安嶺のカラマツはダフニアカラマツ、フブスグルのはシベリアカラマツで、種類がちがうのですが、両者の間に大きな性質の違いがあるとは思われません。 しかし、ハトガルでの観測値からみると、湖岸の高さでの夏の温度は、日本の山の森林限界付近と大差ありません。夏に訪れて、牧野に咲き乱れた野の花の海、放牧家畜の群れ、学校や病院もある村の暮らしなどに接していると、実感がわかないのですが、実は日本アルプスのお花畑で営まれている生活を見ているのでした。ここは、それほど寒い高地なのです。「七不思議」も、大部分はそれで説明できそうです。
「七不思議」のもう一つは、吸血昆虫の不在でした。北国の水辺の夏には、カ・アブ・ブユといった厄介な連中の大群が、人を襲います。頭からスッポリかぶるネット頭巾がなければ、戸外での作業は不可能です。大興安嶺での経験では、行進する駄馬と馬夫の隊列を少しはなれて眺めれば、アブの大群の列が移動しているようでしたし、流れで夕食の洗い物をしている人の黒い上着の背中は、一面に止まったカで灰色に見えました。だから、最初の調査行のときは、覚悟もし、準備もしていったのですが、まったく無用でした。いやな虫はほとんどいないのです。しかし、この疑問も、昨2004年には氷解しました。昨年はとくに暑い夏だったため、湖のまわりではアブの群れにおそわれたのです。吸血昆虫が発生しないのも、単に夏が寒すぎるだけの理由だったのです。モンゴルでも気候の温暖化は進んでいるので、やがてここもアブやカに悩むのが常態になるのでしょうか。 山々はカラマツ林に覆われていると言いましたが、それは正確な表現ではなく、北向きないし東寄りを向いた斜面は、おおむね緩傾斜でカラマツ林に覆われているが、南ないし西寄り斜面は急斜面で、乾燥した草原となっているのです(写真33)。これは、永久凍土地帯に共通の現象で、南斜面は夏に強い日射を受けて、冬に凍った土が深くまで解けるので、雨水による侵食をうけやすくて急斜面となり、また水がすぐ流れ去ってしまうので土が乾燥し、森林が育たないのです。夏にも凍っている永久凍土の深さは、北斜面のカラマツ林のなかでは1〜1.5m、南斜面の草地では2.5〜3mでした。だから、南から北に向かって進んでいくと、草地斜面だけが視野を占め、樹木は尾根すじに列をなして生えているだけのように見えるのですが(写真34)、逆方向にもどるときは森林斜面だけしか見えないというわけです。この草地は、ほとんどすべて放牧に利用されており、きまった季節にだけ少数回使われるようなところでは、すばらしい夏の花の満開が見られます(写真35)。 |
||||
 |

|
||||
| 写真33 | 南北斜面の対照。西岸山脈の南部を湖上から見る。左が南、右が北(2004/7/15)。 | ||||
 |
|||||
| 写真34 | 北に向かって進むと、南斜面の草地だけが目に入り、北斜面の森林は尾根すじの立ち木の列としてしか見えない。この写真で草地に点々と生えているのは、ヤナギの低木で、夏に北斜面の森林の下で解けた水に依存しているらしい(ハトガル北方、2004/7/14)。 | ||||
| いまモンゴルの森林が直面している問題は、頻発する山火事と虫害による減少です。HB地方も例外ではありません。住民による狩猟・鹿の枝角や野生のベリー類の採集、観光客の立ち入りなどの人為的原因で、森林火災の頻度は明らかに高まっています。焼け跡の灰の流入は局所的に湖水の富栄養化を起こしていますし、湖の水収支にも影響する可能性があります。 虫害も、火災に劣らぬ森林破壊の大きな原因です。森林害虫のうち最も被害の大規模なのがガ(蛾)類で、偶発的に大発生するマイマイガとシベリアカレハガが代表的なものです。我々は、2002年の8月上旬に、UBからHBに至る全地域でマイマイガの大発生に遭遇しました(写真36−1、36−2、37)。数ヘクタールくらいから、時にはさらに大きい面積のカラマツ林を、茶色に枯らしてしまうのです。集団発生をおこす原因は何か、この2種のガがしばしば同じ場所に共存して食害するのはなぜか、薬剤を使わずに大発生を食い止めるよい方法はないものか、など疑問は多いが、今はガの専門家の協力をえて、観察と検討を続けています。 |
 |
 |
||||
| 写真36−1 | マイマイガとその大発生。ウランバートル市内のショッピング・センターの灯火に集まったガの大群(2002/8/2、撮影:巌 靖子)。 | 写真36−2 | ほとんどが雌だが、まれに交尾中の雌雄(濃色で小型のが雄)も見られた。 | ||

|
|||||
HB地域で当面の大きな問題は、森林が焼けたり枯れたりした跡では、直射日光のために夏に凍土が深くまで融け、融解水は斜面沿いに流出してしまうために、表土が乾燥して後継ぎの稚樹が育たちにくく、森林の再生がきわめて遅いということです。いわば、先に南斜面について述べたのと同じことが、おこるのです。HB県の森林管理機関は、大量のカラマツ苗を養成して、森林破壊跡地への植林に努めています。しかし、活着率は低いし、対象となる森林消失面積の莫大さ、多大の経費・労働力・高い技術の必要性を考えると、人工植林にのみ依存することは現実的とはいえません。緊急に必要なのは、放置すれば遅々として進まないカラマツ林の自然の再生・復活過程を促進する技術を開発することだ、と私は考えています。
毎年現地を訪れているうちに、行政担当の方々をふくむ知人が増え、現地社会の環境意識の向上のための県主宰のセミナーの講師を務めたり(写真39−1、39−2)、ハトガルの学校での環境教育に協力(写真40)したりするようになりました。日本国内では、NGO「びわ湖・フブスグル湖交流協会」(会長:吉良、事務局長:中川)を発足(1999年5月)させ、終始一緒に行動している中川道子さんの努力で、協会の活動と調査の成果を紹介するニュースレターの発行と報告会を通じて、定期的に現地情報を国内で発信するとともに、ニュースレターのモンゴル語版を発行して(写真41)、調査成果の現地還元にも努めています。このモンゴル語版は、他に同様の出版物がほとんどないので、とくに現地で好評です。中川さんは、精力的な活動に対して、モンゴル政府国政府の「自然・森林・水質保全局」から「名誉尊敬賞」(2004年)を受けています。年のせいで、私のモンゴルでの現地活動は、ここ1〜2年で終わりになるでしょう。しかし、中川さんをはじめ、北モンゴルの気象条件・温暖化・永久凍土の現状と変化などの研究を精力的に続けている武田一夫さん(帯広畜産大学)、草加さんたち協会の仲間の力で、この事業が続いていくことは確かです。 |
||||
 |
 |
||
| 写真39−1 | フブスグル県知事主催の環境セミナー(二日間)に協力。琵琶湖の環境を紹介する中川道子。 | 写真39−2 | 聴衆(ムルン市の県庁内、2004/5/7)。 |
 |
 |
||
| 写真40 | ハトガル村学校(10年制)と共催の「滋賀と環境の夕べ」。エコツアーに参加した滋賀県の大学生たちが主役。村からもいろいろな余興が出た(ハトガル村公民館、2002/8/6)。 | 写真41 | びわ湖・フブスグル湖交流協会ニュースレター。日本語版とモンゴル語版。 |
| *[参考] 熊谷道夫(1998)モンゴルのフブスグル湖。 琵琶湖研究所(編)『アジアの湖沼環境:外観と展望(第16回琵琶湖 研究シンポジウム記録集』、pp.89〜104。 吉良竜夫(2001) 『森林の環境・森林と環境――地球環境問題へのアプローチ』新思索社。 |
おわりに |
| ふりかえってみると、私は、生態学の分野でも環境保全の仕事も、その大部分を外地、それも開発途上地域を対象にしてきたことになります。高校・大学の登山・探検のグループの中で得た方向づけの根強さを、いまさらのように思い返しています。そのせいで、以上の話ではどうしても自然、とくに生態系の問題に深入りしすぎたかも知れませんが、環境の問題と取り組むときは常に総合的に考察することを忘れてはならないという意味では、無駄ではなかったと思います。 「環境保全」というとき、その「環境」とは、私たち人間が直接に感じることのできるもの――生命と生活の維持に必要な日射や温度、健康を害する水や空気の汚れ、五感を楽しませる緑や鳥の鳴き声といったもの――を意味しています。しかし、そういうものの背後には、複雑をきわめた自然のシステムと、そのシステムへの人間活動の影響があって、広い視野からそれを総合的に理解しなければ正しく対応することはできないのです。 別の例を取れば、石油や石炭の使用による二酸化炭素の排出を減らして地球の気候の温暖化を抑制するために、太陽電池や風力発電の利用がもてはやされていますが、そういう「環境技術」にも落とし穴があります。一つの風車が、その耐用年限の間に生み出す電力量と、その風車を作るために、材料金属の採掘・精練に始まって運搬・組み立て・設置・廃棄後処理に至るまでに必要な化石燃料エネルギーとを比較したとき、もし後者のほうが大きければ、本当の意味で環境に貢献していることにはならないでしょう。最近、そういう立場での製品の再検討――ライフサイクル・アセスメント――が行われるようになったのは、望ましいことです。ただし、食品のような場合は比較的容易ですが、複雑な工業製品に対しても正確にやれるかどうか、私には知識がありません。しかし、こういう視点が必要なことには異論はないでしょう。 リサイクル運動にも同様な問題があります。例えばペットボトルは、リサイクルできる便利な軽量容器として、その生産は飛躍的に増えています。いまは、廃ボトルから直接ボトルへと再生産できるばかりでなく、海外への廃ボトルの輸出も激増していると聞きます。結果として、プラスチックの原料である貴重な石油資源の節約には役立っているでしょう。が、リサイクルできるという大義名分に便乗して生産量を増やしていれば、そのための使われる資源とエネルギー量は莫大なものになります。総合的にみれば、こういう場合は、リサイクルよりはリユース(再使用)のほうが、はるかに環境にとって有効な手段といわねばなりません。 私は、長年、自然や環境の保全に対して、さまざまな形で関わってきました。しかし、そのなかから教訓を汲みとるとすれば、結局は「総合的・大局的に環境をとらえ、対応することを忘れるな」ということに尽きます。これを、次の世代の方々への言葉として、私の回想録を終わります。 |
| (2005年9月5日) |
| 講師プロフィール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||